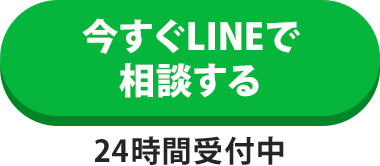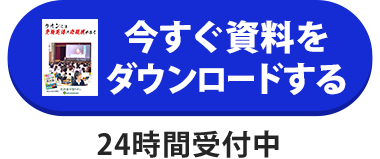Contents
1. なぜ総合型選抜でボランティアが必要なのか

総合型選抜では、大学は 「この学生は自分の意思で動ける人物か」「社会に関心があるか」 を見ています。
学校成績だけではその部分が見えないため、行動の根拠として ボランティアは最も“説明しやすい経験” として機能します。
・勉強だけでは見えない人柄
・社会観
・他者への理解
・行動力
・継続力
これらが、ボランティア経験を通して自然に現れます。
1-1. ボランティアなしはどう見られるのか
1-1-1. 活動が「なし」でも受験はできるが、語る材料が乏しくなる
総合型選抜は 行動の理由と背景 が問われます。
学びと体験が接続しているかで評価されるため、
「特に何もしていない状態」では志望理由の説得力が弱くなる傾向があります。
1-1-2. 1日でも“行動したという事実”が評価につながる
大学側は「どれだけ豪華な実績か」よりも、
自分で選んで行動したかどうか を見ています。
たった1日であっても、以下のような変化が生まれます。
・実際に見た課題
・感じた違和感
・新しい価値観
・志望理由との接続の糸口
・面接で語れる具体的な出来事
これだけで、面接での回答が全く違うものになります。
〈行動〉
まずは1日で完結する活動でもOK。何かを「選んで、動いた」事実が価値になる。
とはいえ受験する大学によっては、条件がことなるので必ず確認するようにしましょう。
2. 総合型で“評価されるボランティア”の3つの基準
2-1. 志望学部とのつながりが明確
志望学部と体験がつながると、
大学側にとって 「この学生は本当に学びたいんだな」 と信頼できる材料になります。
以下、学部別に保護者が安心して勧められる例を解説します。

2-1-1. 経済学部向き:地域課題・支援・労働・消費の現場に触れる
経済学部では、社会と仕組みを理解する姿勢が評価されます。
【評価される活動例】
・フードバンクの仕分け → “貧困・需要と供給” を語れる
・子ども食堂 → “地域のつながり・食の格差”を理解
・地域祭りの運営 → “地域経済・コミュニティ”の視点
・商店街支援 → “経済循環・地域活性”と直結
評価される理由
「現場にある課題」と「経済の理論」が結びつくため、志望理由書が深みを増します。
2-1-2. 経営学部向き:組織・運営・チームの動きを体感できる活動
経営学の本質は「人を動かす」「組織を動かす」です。
【評価される活動例】
・イベント運営
・子ども教室のサポート
・広報の手伝い(チラシ・SNS)
・地域行事の受付・誘導
評価される理由
役割分担・段取り・コミュニケーションなど、経営の実践に直結するため。
2-1-3. 法学部向き:ルール・福祉・権利・社会問題に触れられる活動
法学部は「弱者」「制度」「公正さ」に向き合う姿勢が評価されます。
【評価される活動例】
・高齢者施設 → “権利・介護制度・尊厳”の理解
・障害支援 → “合理的配慮・法的支援”
・外国人支援 → “文化・言語と制度の壁”
・子ども支援 → “養護・教育格差”
評価される理由
社会の仕組みや制度に対する問題意識を語りやすくなるため。
志望する大学により、どんなボランティアが適しているかわからない場合は、お気軽にご連絡ください。最適なボランティアをあっせんいたします。
2-2. 「なぜその活動を選んだのか」が語れる
総合型選抜で大学が一番知りたいのは、
「どんな活動をしたか」以上に、「なぜ、その活動をやろうと思ったのか」 という部分です。
同じ子ども食堂のボランティアでも、
- 友だちに誘われたから、なんとなく行った
のと - 小さいころ家計が苦しかった経験から、「食の支援」に関心を持って自分で探して参加した
のとでは、まったく印象が変わります。
活動そのものよりも、選ぶまでの背景・心の動き・問題意識 が、総合型では強い評価ポイントになります。
2-2-1. 動機がある活動はストーリーが強い
大学側が見ているのは、単なる「いい子アピール」ではなく、
その子なりの 「行動に至るまでのストーリー」 です。
動機は、必ずしも立派なものでなくて大丈夫です。
次のような、小さな違和感や気づきから始まることがほとんどです。
・身近な問題(家族・地域の出来事)
例)
「祖父母の介護をきっかけに、高齢者施設に関心を持った」
「近所の公園がごみだらけなのが気になって清掃活動を探した」
・読んだ本やニュースで気付いた疑問
例)
「子どもの貧困についての記事を読んで、子ども食堂の存在を知り参加した」
「SDGs関連の本を読んで、環境ボランティアに興味を持った」
・学校生活の中で感じた違和感
例)
「クラスの中で孤立している人を見て、人とのつながりや居場所づくりに関心を持った」
「文化祭の運営を経験し、イベント運営をもっと深く学びたいと思った」
・進路と関連するテーマ
例)
経済学部を志望していて、
「地域経済や格差に興味が出て、フードバンクでの活動を選んだ」
こうした動機があると、志望理由書や面接で
- 「なぜ、そのボランティアだったのか」
- 「なぜ、その学部を選んだのか」
を一本の線で語ることができます。
保護者としてできるのは、
「どうしてそこを選んだの?」と、責めるトーンではなく、純粋な興味で聞いてあげること です。
質問されることで、子ども自身が自分の動機に気づき、言語化の練習にもなります。
〈基準〉
活動の“立派さ”よりも、「その子にとって必然性があるかどうか」 がストーリーの強さを決めます。
2-2-2. ネットの“例”を模倣すると弱くなる理由
最近は「総合型選抜 ボランティア 例」「総合型選抜 ボランティア 知恵袋」などで調べると、
「こんな活動をすると有利です」といった“テンプレート”がたくさん出てきます。
しかし、それをそのまま真似してしまうと、次のような問題が起きます。
- 本人の実感がないので、具体的な質問に答えられない
- 似たようなエピソードが大量発生し、大学側から“作った感”が出てしまう
- 活動と志望理由のつながりが浅く、他の受験生と差がつかない
面接官は、必ずこうした質問をしてきます。
- 「その活動で一番印象に残っている場面は?」
- 「そのとき、あなたはどう感じましたか?」
- 「もう一度同じ活動をするとしたら、何を工夫しますか?」
ネット上の「それっぽい例」を表面だけ真似していると、
こうした質問に対して答えが薄くなり、すぐに見抜かれてしまいます。
保護者としては、
「ネットにこう書いてあったから、これをやりなさい」と押し付けるのではなく、
- 「あなたが気になるテーマってどんなこと?」
- 「腹が立ったニュースとか、気になった出来事ってある?」
と、子ども自身の問題意識から逆算して活動を選ぶ 手伝いをしてあげるとよいです。
〈基準〉
ネットの“合格例”をなぞるより、
「うちの子だからこそ選んだと言える活動」 のほうが、何倍も強い武器になります。
2-3. 継続または「ふり返りの深さ」で判断される
「総合型選抜では、ボランティアは何回やればいいですか?」
これは保護者から本当によく聞かれる質問です。
結論から言うと、大学は “回数”を見ているわけではありません。
見ているのは、
- その経験を通じて何を感じたか
- どう考え方や行動が変わったか
- それが進路選択にどうつながっているか
という 「ふり返りの深さ」 です。
2-3-1. 「何回やったか」より「どう変わったか」が評価される
確かに、長く続けている活動は評価されやすいです。
しかし、単に
- 「毎週行っていました」
- 「3年間続けました」
とだけ言っても、そこに 気づきと変化のエピソード がなければ、評価は伸びません。
逆に、
- 「最初はいやいや行ったが、ある出来事をきっかけに考え方が変わった」
- 「トラブルがあり、自分なりに工夫した経験がある」
- 「活動を通して、自分の弱点に気づいた」
といった “心の変化”や“行動の工夫” が語れると、面接官の印象は一気に変わります。
大学は、ボランティアの「回数」ではなく、
「その活動を通して見えてきた、その子の成長のストーリー」を見ている と考えてください。
2-3-2. 単発1回でも深い学びがあれば十分
「うちはもう高3だから、今からボランティアを始めても遅いですよね?」
という相談も多いですが、決して遅くはありません。
たとえ1回の単発ボランティアでも、
- それまで知らなかった現実を目の当たりにした
- 自分の思い込みに気づいた
- もっと知りたいテーマが見つかった
- 別の形で関わり続けたいと思った
という体験があれば、総合型で十分“語れる経験” になります。
大事なのは、「たくさん参加したか」ではなく、
「その1回をどう自分の中で咀嚼しているか」 です。
そこで役に立つのが、短い「気づきメモ」です。
【おすすめの3行メモ】
1行目:今日やったこと(事実)
2行目:驚いたこと・心が動いたこと(感情)
3行目:次にやってみたいこと(行動・意欲)
例)
1行目:子ども食堂で配膳と片付けをした。
2行目:思っていた以上に、小学生だけで来ている子が多く、家庭事情を想像して胸が苦しくなった。
3行目:支援の仕組みをもっと知りたくて、市の制度について調べてみたい。
この3行メモが溜まっていくと、それ自体が
- 志望理由書
- 活動報告書
- 面接のエピソード
の“材料”になります。
保護者としては、
「今日どうだった? 何か印象に残ったことある?」と、軽く聞いてあげるだけで十分なサポート になります。
〈行動〉
活動のたびに、ノートやスマホに「3行ふり返り」を書く習慣をつける。
回数より、“ふり返りの積み重ね”が総合型での武器になります。
3. ボランティアに“嘘”を書いてはいけない理由
総合型選抜では、
「どんな資格があるか」よりも、
“人としての姿勢と誠実さ” が大きく評価されます。
そのため、ボランティアの嘘や「盛り」は、
合否以前に“人柄評価”で評価を下げる非常に大きなリスクがあります。
単に「嘘はダメ」ではなく、
“嘘を書いた瞬間、面接と書類の構造が破綻する”
という点を理解しておく必要があります。
3-1. 嘘は高確率で見抜かれる
総合型選抜の面接官は、数百〜数千人の受験生を見ています。
そのため、嘘や“作り話”には 必ず気づく感覚 を持っています。
特にボランティアの嘘は、
“経験として定型化しにくい内容”なのでバレやすい領域です。
3-1-1. 面接では必ず“質問の深掘り”が来る
面接官は
「その活動で一番大変だったことは?」
という一見簡単な質問から、必ず深掘りしてきます。
嘘が破綻する瞬間は、この深掘り質問です。
【深掘りの例】
・「そのとき、誰がいて、どんな指示がありましたか?」
・「その場面で、あなたは具体的に何をしましたか?」
・「その子どもは、どんな表情をしていましたか?」
・「なぜその活動を選んだのですか?」
・「その経験が、この学部とどう関係しますか?」
嘘の経験では、
場面の具体性・感情・温度感・矛盾のなさ
を語ることができません。
本物の経験は小さなディテール(匂い・空気・表情・驚き)まで自然に出ますが、
作り話は「言葉が薄い」「すべて表面的」「話の筋が不自然」になります。
【嘘にありがちな特徴】
・話がふわっとしている
・すべて“良い話”にまとめようとする
・感情が入っていない
・具体的な人物が登場しない
・改善点や失敗の話がない
これは面接官が最も敏感に見抜く部分です。
3-1-2. 証明書の提出を求める大学が増えている
総合型選抜では、
不正防止の観点から 「証明書」や「活動記録の提出」 を求める大学が増えています。
特に、
・中央大学
・関西学院大学
・上智大学
・立命館大学
などは、出願要件で証拠を示す欄を設定している学部があります。
嘘を書いた瞬間、
「証明書の提出が必要な大学」
→ 出願できない
という事態さえ起こります。
3-1-3. エピソードの深さで真偽がわかる
ボランティアの“本物の経験”と“嘘の経験”では、文章構造が根本的に違います。
【本物の経験】
・驚き
・気づき
・葛藤
・失敗
・学び
・続けたいと思った理由
これらが一貫しています。
【嘘の場合】
・全部きれいにまとまっている
・感情がない
・トラブルがない
・登場人物が抽象的
・学びが浅い
実際の現場経験には、必ず「不完全さ」「予想外」があります。
それこそが本物の証拠です。
面接官はその違いを一瞬で見抜きます。
3-2. 嘘は合否以前に“信頼の欠落”となる
総合型選抜は、
大学が“未来の学部生としてふさわしいか”を見極める選抜方式 です。
ゆえに大学側は、
“誠実さ”
“真摯な姿勢”
“社会との向き合い方”
を最重視します。
嘘をつくとどう見られるか?
・本質的な学びに向き合えない
・問題が起きたとき責任を取らない
・コミュニティを壊す可能性がある
・信用を損なう人物である
という、
大学という共同体に不利益をもたらす人物
と判断されやすくなります。
総合型選抜で「不合格」となる理由の中で、
最も多いのは
“誠実さの欠如”
です。
学力不足よりも致命的です。
保護者が伝えるべきポイントは「正直であることの価値」
嘘を書いてしまう背景には、
「実績が足りない」「周りに負けたくない」という焦りがあります。
そんなとき、保護者がそっと一言、
「少なくてもいい。1回でもいい。
あなた自身の経験のほうが、大学には伝わるよ」
と伝えてあげるだけで、子どもは正しい方向に戻ることができます。
大学が見たいのは
“規模の大きな活動”ではなく、“その子なりの成長”
です。
〈基準〉
少ない経験でも「本物」であることが、どの受験生より強い。
大学は「偽物の100回」より、「本物の1回」を評価する。
4. ボランティア証明書の扱い
総合型選抜では、証明書(ボランティア活動証明書)は 「あると非常に強い」 一方で、
「絶対に必要」ではありません。
ただし、
●志望理由書の説得力
●面接での信頼性
●大学側の安心感
が大きく変わるため、親として知っておくべきポイントが多い部分です。
証明書をどう扱うかで“合格の質”が変わります。

4-1. 証明書の重要性
まず、総合型での証明書の本質を整理します。
4-1-1. 証明書があると“信頼性が跳ね上がる”
証明書は、大学に対して
- 「本当にその活動をしました」
- 「時間・場所・内容に嘘はありません」
- 「外部団体の客観的な裏付けがあります」
と示す 強いエビデンス(証拠) になります。
総合型選抜は、書類と面接が中心の選抜方式なので、
“本人が語る話に信憑性があるか”
が合否に大きく影響します。
証明書があるだけで、大学側は
- 「誠実」
- 「準備ができる人」
- 「情報を整えられる人」
と評価してくれます。
※保護者の方が一番誤解しやすい部分ですが、
👉 証明書=評価される、ではない
👉 証明書=信頼が上がる、が正しい
これが本質です。
4-1-2. 証明書がなくても「活動記録」で代替可能
「証明書が出ない小さな活動だから不利なのでは?」
という心配がありますが、これは誤解です。
実は、大学が重視しているのは
活動の深さ × ふり返りの質 です。
証明書がなくても、次のような記録があれば十分提出できます。
【記録ノート(おすすめ形式)】
・活動日
・場所
・参加時間
・活動内容
・現場で見たこと/驚いたこと
・学んだこと
・次にやりたいこと
これは「ポートフォリオ」として提出できます。
むしろ証明書よりも、
“本人の言葉で書かれた記録” に大学は価値を見出します。
ただし証明書があると「裏付け」になるためセットで強くなる、というイメージです。
4-2. 証明書をもらうときの基準
証明書は「誰が発行したか」によって信頼性が変わります。
特に総合型では、大学側が提出物を慎重に扱います。
4-2-1. 公的団体は証明書が整っている
証明書を安心して出してくれるのは主にここです。
◎ 社会福祉協議会(社協)
◎ 市区町村のボランティアセンター
◎ 認定NPO(NPO法人の中でも“認定”された団体)
◎ 学校と連携している団体
◎ 大きなイベント主催者
こうした団体は 標準様式・代表者印・団体情報 が揃っており、大学側も迷わず受理します。
逆に、
△ 個人主催のボランティア
△ 任意団体
△ 活動実績の少ない団体
× 無登録・住所が不明な団体
× SNSでの呼びかけだけの活動
これらは大学から「正式な証明書として扱えません」と言われる可能性があります。
4-2-2. “提出用”証明書に必須の5項目
大学提出に使える証明書は、最低限次の項目が必要です。
・日付
・活動内容(何をしたか)
・時間(何時間参加したか)
・主催者名(団体正式名称)
・代表者印または署名(責任者の名前)
これらが揃っていれば、大学は「正式な記録」として扱います。
追加であるとさらに良いもの:
・活動場所
・団体の連絡先
・担当者名
・写真(許可されている場合)
大学は、曖昧な情報の証明書を嫌がります。
逆に情報が揃っていると「管理ができる子」として評価が上がります。
〈行動〉申込前に「証明書の発行は可能ですか?」と必ず確認する
これが、もっとも重要です。
保護者がチェックしておくべきポイント:
【申込前チェックリスト】
□ 証明書は発行可能か
□ 英語版も必要か(海外大学/帰国生受験の場合)
□ 再発行は可能か
□ 記載内容を確認済みか
□ 団体の住所・連絡先は明記されるか
証明書の有無を事前に確認することで、
後から慌てたり、書類不備になったりするリスクがなくなります。
▼深掘りの全体まとめ
● 証明書は“信頼性を上げるツール”
● ない場合でも“記録ノート”で代替可能
● 公的団体の証明書は大学からの信頼度が高い
● 申込前に必ず「証明書の発行可否」を確認
● 提出用証明書は5項目が必須(内容・日付・時間・主催者・署名)
ことが重要になります。
5. 学部別に評価される具体的なボランティア例
総合型選抜では、ボランティアの“立派さ”よりも、
「志望学部の学びとつながっているか」 がもっとも重要です。
ここでは、保護者が「うちの子にはこれが合う」と選べるように、
経済学部/経営学部/法学部の3学部別に、最適なボランティアと、その理由、志望理由につながる言い方まで しっかり深めます。
5-1. 経済学部に評価されるボランティア
経済学部が扱うテーマは
「社会の仕組み」「地域経済」「貧困と格差」「資源の分配」
など、生活の土台にある“社会問題” が中心です。
そのため、現場の課題に触れられるボランティアほど、志望理由書に書きやすく評価が高くなります。
5-1-1. 評価される理由
経済学部は、教科書だけで理解しきれない「リアルな社会」を体験している受験生を評価します。
以下の理由で“ボランティア経験”と相性が抜群です。
・社会問題(食・教育・貧困)に触れられる
・地域経済の仕組み(商店街・地域イベント)が理解できる
・需要と供給の関係を実感できる
・「なぜ支援が必要なのか」という構造的視点が育つ
・「数字の背景」や「制度の限界」が見える
経済学の学びは、生活の中に存在します。
ボランティア活動はその“生活・現場”を直接経験できるため、非常に強い接続点になります。
5-1-2. 推奨される活動
① 子ども食堂(最も強い)
・地域格差
・食の不平等
・家族の経済状況
など“経済的背景”が直接見える活動。
② フードバンク(需要と供給が学べる)
・寄付食品の仕分け
・必要な家庭への分配
→「資源の再分配」という経済学の核心を学べる。
③ 地域清掃(地域活性の入口)
清掃は一見単純ですが、地域住民との関わりが生まれ、
「地域の人のつながりが経済をつくる」ことを実感しやすい。
④ 商店街イベント支援(地域経済を体験)
・イベントの参加人数
・売上の傾向
・地域の人出
がわかるため、地域経済を理解しやすい。
5-1-3. 志望理由につながる言い方
悪い例(よくあるが弱い)
「貧困問題に興味があります」
→抽象的で“あなた自身の話”になっていない。
評価される言い方(具体例)
・「子ども食堂で配膳をしたとき、家庭環境の違いが子どもの笑顔に影響することを感じた」
・「フードバンクの活動で、廃棄されるはずの食品が多いことに驚いた。資源の再配分の重要性を実感した」
・「商店街のイベントで、来場者数によって売上や雰囲気が変わることを体感し、地域経済への興味が強くなった」
→ “現場の具体的な体験”+“経済の視点” がセットになると強い。
5-2. 経営学部に評価されるボランティア
経営学部は
「人」「組織」「リーダーシップ」「マーケティング」「運営」
など“運営と管理”に関わる学部です。
ボランティアは、有償労働ではないからこそ、
「動機」「役割分担」「人を動かす難しさ」 が実感でき、経営学部と特に相性が良い領域です。
5-2-1. 評価される理由
経営学は、数字を見るだけではなく、
「現場で人と関わりながら仕組みを動かす学問」 です。
ボランティアの現場は、まさにその経験ができます。
・役割分担
・コミュニケーション
・トラブルへの柔軟な対応
・現場のリーダーの動き
・チームワーク
これらはすべて経営学で扱うテーマです。
ボランティアは無償だからこそ「人の主体性」が強く求められます。
この点が大学側の評価につながります。
5-2-2. 推奨される活動
① イベントスタッフ(王道で最強)
役割が多く、状況判断も求められるため、学びの密度が高い。
(例)受付・誘導・準備・撤収・トラブル対応など
② 告知・広報(マーケティングの入り口)
・SNSでの発信
・チラシ配布
・ポスター設置
→「認知を広げる経験」は経営学の中心。
③ 企画系のサポート(計画力・構成力が育つ)
子ども教室や地域イベントの運営補助は、準備段階から学べる点が強い。
④ 地域の運営補助(小規模ビジネスの体験)
商店街、自治会のイベントなどは、運営者の裏側を学べる絶好の機会。
5-2-3. 志望理由につながる言い方
弱い例
「イベント運営に興味がありました」
→ありきたりで差別化できない。
強い例
・「受付を担当した際、参加者の表情から『待ち時間』や『説明の分かりやすさ』が重要だと気づいた」
・「役割分担が曖昧でトラブルになった経験から、組織における“情報共有の大切さ”を学んだ」
・「SNSで告知した投稿の反応率が変化したことで、マーケティングの面白さを感じた」
→「気づき」→「学び」→「経営学部への意欲」が自然につながる。
5-3. 法学部に評価されるボランティア
法学部は
「権利」「制度」「社会的弱者」「公正」「ルール」
を扱う学問です。
そのため、
実際に“支援の現場”に触れる活動が最も強く評価されます。
5-3-1. 評価される理由
法学部は、法律の条文を覚えるだけではなく、
社会問題を“当事者の視点”で理解する学部 です。
ボランティアで弱者支援の現場に触れると、
・制度の限界
・人権と尊厳
・支援が必要な理由
・福祉制度の実態
・多様性への理解
など、教科書では絶対に得られない“司法の根拠”を体感できます。
大学はここを非常に高く評価します。
5-3-2. 推奨される活動
① 高齢者支援(尊厳・人権・制度の理解)
・話し相手
・レク補助
・散歩の付き添い
→ 介護保険制度、介護労働、家族の負担などが“肌感”で分かる。
② 子ども支援(教育格差・家庭の事情)
・放課後教室
・読み聞かせ
・子ども食堂サポート
→ 子どもの権利や教育保障に触れられる。
③ 障害福祉(合理的配慮・法的支援)
→ 障害者基本法・バリアフリー法の“現場”を学べる。
④ 外国人サポート(言語の壁・制度の壁)
→ 多文化共生と制度の不備に気づきやすい。
5-3-3. 志望理由につながる言い方
弱い例
「困っている人を助けたいと思った」
→ 抽象的で理由が弱い。
強い例
・「高齢者施設で“制度があっても救えない瞬間”があることを知り、制度の改善に興味を持った」
・「障害のある子どもと接し、“合理的配慮とは何か”を考えるきっかけになった」
・「外国人支援の現場で、日本語が話せないだけで情報から取り残される現実を知り、多文化共生に関心を持った」
→ 法学部が重視する “現場の視点 × 制度への問題意識” を含んでいる点が非常に評価されます。
6. 親が今日からできる“合格に近づくサポート”
総合型選抜は「本人の頑張り次第」と言われがちですが、実際には 親の関わり方 が大きく影響します。
といっても、難しい受験指導や専門知識が必要なわけではありません。
大事なのは、
・安全を一緒に守ること
・経験を言葉にするのをそっと手伝うこと
・ムリのないペースを一緒に考えること
この3つだけです。
「勉強しなさい」と言うよりも、
ボランティアという“行動の土台”を支えてあげるほうが、
総合型選抜ではずっと大きな力になります。

6-1. 情報共有:親子で“同じ地図”を持つ
ボランティアは、学校とは違う場所・違う大人・違うルールの中に子どもが入っていく活動です。
だからこそ、親子で情報を共有しておくことが、安全面でも受験準備の面でも、とても大切になります。
6-1-1. 共有しておきたい4つの基本情報
最低限、次の4つは親子で共有しておきましょう。
・活動先(団体名・場所・連絡先)
・時間(集合時刻・終了予定時刻)
・連絡手段(スマホ/LINE/電話など)
・帰宅予定(大体何時ごろ家に着くか)
紙に書いて冷蔵庫に貼っておく、
家族グループLINEに送っておく、
といった形で「いつでも見られる状態」にしておくと安心です。
これだけで、
・電車の遅延やトラブルがあったときにすぐ動ける
・親が不安になって何度も連絡してしまう…ということが減る
・子どもも「見守られている安心感」の中で活動できる
という効果があります。
6-1-2. 情報共有は“口出し”ではなく“安心材料”
親としては、情報を知ると「そんな遠いところ危なくない?」「本当に大丈夫?」と、不安から口出ししたくなることもあると思います。
そのときは、
まずは一度深呼吸してから、
「何かあったら、ここに連絡くれればすぐ動くからね」
「道に迷ったら、電話して。一緒に地図を見るよ」
と “見守る言葉” を添えてあげると、
子どもにとっては大きな安心材料になります。
6-2. ふり返りの手伝い:“ただ聞いてあげる”がいちばんの受験対策
総合型選抜では、ボランティア自体よりも
「その経験をどう言葉にしているか」 が合否を分けます。
その言葉の土台をつくるのが、親の「何気ない一言」です。
6-2-1. 魔法のひと言は「どうだった?」
難しい質問は必要ありません。
活動から帰ってきた子どもに、ただ一言、
「どうだった?」
と聞いてあげるだけで十分です。
そこで子どもが話し始めたら、
途中で結論を急がせたり、正解を求めたりせず、
・「へえ、そんなことがあったんだね」
・「それは大変だったね」
・「それ、よく気づいたね」
と、感想を受け止める役 に回ってあげるだけでOKです。
話すこと=そのまま「言語化の練習」になり、
のちの 志望理由書や面接での受け答えの下準備 になります。
6-2-2. 親がしてあげられる“+1質問”
もし余裕があれば、こんな質問を1つだけ足してあげてください。
・「一番びっくりしたことは?」
・「一番うれしかったことは?」
・「一番疲れた場面ってどこ?」
・「もし次に行くなら、何を工夫したい?」
この“+1質問”が、子どもの気づきを一段深くしてくれます。
それがそのまま、
・「エピソード」
・「気づき」
・「成長のきっかけ」
として志望理由書の芯になっていきます。
6-3. 無理のないペース作り:回数より“続け方”
総合型選抜のためだからといって、
毎週びっしり予定を詰めたり、
疲れていても無理に参加させたりすると、
逆に「もうやりたくない」となってしまいます。
大切なのは、“合うペースで続けること” です。
6-3-1. 月1回でも十分“評価される経験”になる
・月1回の子ども食堂
・長期休みに集中的な参加
・学校行事+時々の地域活動
このくらいの頻度でも、
ふり返りをきちんとしていれば総合型選抜では十分に評価されます。
大学が見ているのは、
・どれだけたくさん参加したか
ではなく
・その経験から何を学んだか
・そこから進路とどうつながっていったか
です。
6-3-2. “疲れたサイン”を尊重する
受験勉強・部活・学校行事と並行して活動するので、
子どもが「ちょっとしんどい」と感じる時期もあります。
そんなときは、
・「今月は無理しなくていいよ」
・「テスト前は休んで、終わってからまた再開しようか」
と、ブレーキを一緒に踏んであげる役 になってあげてください。
一度立ち止まっても、
「またやってみようかな」と本人が思える余白があれば、
その経験は“途切れた”のではなく、“深まった”と評価されます。
〈基準〉
親のサポートで大切なのは、次の3つです。
- 安全のための情報を一緒に持つこと
- 経験を言葉にする場をつくること
- 無理のないペースで“細く長く”続けさせてあげること
この3つが揃うと、
ボランティアは「ただの受験対策」ではなく、
お子さんにとって 一生役立つ経験 に変わります。