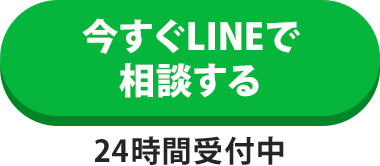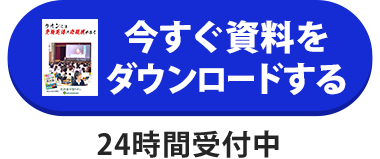Contents
高校生が参加できるボランティア完全ガイド|1日・単発・東京/神奈川/埼玉/千葉の探し方
1. どんなボランティアが高校生に向いているのか

高校生がボランティアに参加する目的は「経験」「社会性」「進路」「自信づくり」などさまざまです。しかし、親としては 安全性・負担・継続性 が気になるところです。まずは、何を基準に探すべきかをそろえるところから始めます。
1-1. まず“安全・年齢・日数”の基準をそろえる
1-1-1. 高校生は「安全性」「受け入れ年齢」「保険加入」で判断する
高校生可のボランティアは、募集要項に次の情報が明確に書かれていることが大切です。
・活動内容に危険がない
・高校生(15~18歳)を受け入れている
・ボランティア保険に加入できる(または主催側で加入済)
・スタッフの配置基準が明確
とくに初めて参加する場合は、自治体・公的なNPO・学校連携 を優先すると安心です。
1-1-2. 1日・単発の活動は“主催の信頼性”で判断する
「1日だけ」「単発OK」の活動は、手軽で参加しやすい一方、主催者によって質や安全性が大きく異なります。
・自治体のボランティアセンター
・区市町村主催イベント
・公的NPO(認定NPO)
・学校が紹介する地域活動
このような団体なら、保険・安全管理・緊急時の対応がしっかりしています。
〈行動〉
最初のボランティアは“自治体主催・学校連携・認定NPO”を優先して選びます。
1-2. 参加目的を本人と共有する
1-1-1. 「経験」「進路」「証明書」の優先順位を決める
ボランティアは種類が多く、目的によって選ぶべき場所は大きく変わります。
・進路の面接で話せる経験を作りたい
・人と関わる経験を積ませたい
・自信をつけてほしい
・活動証明書が必要
・1日だけ試してみたい
目的を明確にすると、活動選びがブレなくなります。
1-2-2. 本人の“得意な関わり方”に合わせる
高校生は体力・対人力・集中力に個人差があります。
得意な形から始めると、無理なく続けられます。
・人と話すのが苦手 → 図書館・フードバンクの整理
・体力に自信 → ゴミ拾い・清掃
・人と関わるのが好き → 子ども食堂・イベント補助
・勉強が得意 → 学習サポート
〈行動〉
本人の“やりやすい形”を3つ書き出し、その条件に合う活動を探します。
2. 1日・単発で参加できるボランティア
短い時間で完結する活動は、高校生にとって参加しやすく、学校との両立もしやすいメリットがあります。

2-1. 当日完結型(都市部中心)
2-1-1. ゴミ拾い・清掃活動(東京・神奈川・埼玉・千葉)
ゴミ拾いは初心者向けの代表格です。
・街中の清掃
・海岸ごみ拾い(神奈川・千葉が多い)
・公園・河川敷のクリーン活動
活動証明書を出してくれる団体もあります。
2-1-2. 行政・NPOのイベント手伝い(受付・誘導)
都心(特に東京)では、毎週のようにイベントが開催されており、受付・誘導などの補助業務があります。
・文化イベント
・スポーツ大会
・地域祭
・講演会の運営補助
事前説明が丁寧なので、高校生でも安心です。
〈行動〉
「〇〇市 ボランティアセンター」「〇〇区 清掃 ボランティア」で検索し、1日型の募集を確認します。
2-2. 学校との相性が良い“短時間活動”
2-2-1. 図書館・公民館の補助
主に次のような軽作業です。
・本の整理
・館内案内
・読み聞かせの補助
穏やかな環境で安心して参加でき、勉強が好きな子にも合います。
2-2-2. 子ども食堂・フードドライブ
食材の仕分け・配布準備など、達成感があり短時間から始められます。
〈行動〉
「子ども食堂 × 住んでいる地域」で検索し、体験参加の可否を問い合わせます。
3. 医療・福祉系のボランティアを希望する場合
医療系は進路を意識して探すご家庭が多く、人気があります。
ただし高校生に許される範囲は限られるため、事前確認が必須です。

3-1. 高校生が可能な“補助業務”を選ぶ
3-1-1. 病院ボランティアは“高校生可”に限定される
医療行為はできないため、主な活動は次の通りです。
・道案内
・書類整理
・図書の貸出補助
・院内の掲示物整理
受け入れ病院は限られるため、募集を見つけたら早めの応募が必要です。
3-1-2. 高齢者施設は“見守り・レク補助”から
福祉分野は高校生可の活動が多いです。
・話し相手
・散歩の付き添い
・レクリエーション補助
・施設内の軽作業
〈行動〉
「高校生可」「福祉施設 ボランティア」で検索し、安全基準を確認します。
3-2. 事前に確認したい“年齢・保険・誓約”
3-2-1. 未成年は保護者同意書が必須
ほとんどの医療・福祉施設では親の同意書が必要です。
書式が違うため、必ず事前に問い合わせます。
3-2-2. 活動保険の加入を確認
自治体ボランティアセンター経由なら、加入手続きがスムーズです。
〈基準〉
医療・福祉の活動は「保護者同意」「保険加入」「活動内容の明示」の3点が揃っているかで判断します。
4. 海外ボランティアを検討する前に
高校生の海外ボランティアは、視野を大きく広げる貴重な経験になります。
異文化の中で生活し、英語やコミュニケーション力を伸ばし、自己肯定感を高めるきっかけになることも多いです。
しかし、国内とは違い 安全対策・健康管理・現地環境・主催団体の質 の見極めが欠かせません。
親としては「本当に高校生が行って大丈夫?」「治安は?」「体調は?」「トラブル時は?」と心配が増える領域でもあります。
だからこそ、海外を検討する際は“憧れより安全性を優先する”という順番が大切です。

4-1. 高校生の海外活動は“安全性”が最優先
海外ボランティアでは、国内以上に情報格差が大きく、団体によって安全管理の精度が大きく異なります。
親子でしっかりとした基準を持ち、慎重に選ぶことが必要です。
4-1-1. 高校生向けは“教育プログラム型”を選ぶ
高校生が安全に参加できる海外プログラムは、基本的に「教育型」が中心です。
これは、活動内容や宿泊環境があらかじめ整備され、未成年でも安心して参加できるように設計されているためです。
代表的なプログラムは以下のとおりです。
・語学研修+ボランティア
ホームステイや寮生活をしながら、午前は語学、午後は軽作業のボランティアなど。
海外初心者でも取り組みやすく、安全管理も整っています。
・文化交流+軽作業
現地の学校訪問や日本文化紹介(折り紙・書道など)、施設の簡単な手伝いが中心です。
「人とかかわること」が目的の場合は特に向いています。
・教育支援(日本文化紹介・子ども支援)
読み聞かせ、簡単な授業補助、文化体験を伝える活動など。
直接支援というより“交流型”の位置づけが多いです。
一方で、純粋な労働型ボランティア(建築作業・農作業・重労働など)は避けるべき です。
未成年が危険な作業に従事するのは望ましくなく、現地での事故や体調不良につながる可能性があります。
【基準】
“高校生向け”と明記されている教育プログラム型を選び、労働型は選択肢から外します。
4-1-2. 渡航国の治安と主催者の実績を確認
海外では、日本と同じ感覚で安全を期待することはできません。
国によっては、夜間の外出禁止、感染症の流行、政治情勢の不安定さなど、さまざまなリスクがあります。
とくに確認したいのは次の3点です。
- 渡航国の治安情報(外務省「海外安全ホームページ」)
レベル1(十分注意)以上が出ている地域は慎重に判断します。 - 主催団体の実績・安全基準
・何年間高校生を受け入れているか
・緊急時の対応マニュアルがあるか
・現地スタッフが常駐しているか
・夜間の見回り、外出ルールの明示があるか
などを確認します。 - ホームステイ先・寮の安全性
・治安の良い地域にあるか
・夜間の施錠・セキュリティ体制
・同室生との相性や生活ルール
これらは、参加者の安心バランスに大きく関わります。
【行動】
参加前に「治安」「主催団体の実績」「宿泊環境」について、必ず書面や公式サイトで確認します。
4-2. 準備とリスクの共有
海外ボランティアで最も重要なのは “親子で同じ情報を共有しておくこと” です。
国内以上に、トラブル時の対応は速度が命です。ネットのつながらない場所も多いため、事前の準備が安全を左右します。
4-2-1. 旅程・保険・緊急連絡を紙で共有
海外では、次のような状況が起こり得ます。
・Wi-Fiが不安定
・現地SIMの不具合
・時差で連絡が取りにくい
・集合場所が地図アプリで開けない
など。
そのため、スマホだけでなく 紙での情報共有 が必須です。
【紙で持つべき情報】
・旅程(フライト番号・時間・乗り継ぎ情報)
・宿泊先の住所・電話番号
・主催団体の緊急連絡先
・現地スタッフ名
・集合場所の地図
・保険証券番号・問い合わせ先
紙の資料は、スマホが使えないときの“唯一の命綱”になります。
【基準】
「スマホだけに頼らない」ことを前提に、安全情報を紙で準備します。
4-2-2. 証明書が必要な場合は形式を先に確認
高校生の海外ボランティアは、
大学入試・総合型選抜・推薦入試で「活動報告」として提出するご家庭も多いです。
しかし、証明書は 団体によって形式が異なり、後から再発行できない場合もあります。
事前に次の点を確認します。
・英語・日本語の両方を発行してもらえるか
・団体名・活動内容・日付・場所・時間が明記されるか
・公的機関として信頼される書式か
・大学側が要求する形式(A4縦/英文記載など)と合っているか
証明書の形式が合わない場合、せっかくの活動が出願書類として認められないケースもあります。
【行動】
海外プログラムを選ぶ際は「治安」「保険」「証明書の形式」を最初にセットで確認し、必要事項をチェックします。
5. 地域別で探す(東京・神奈川・埼玉・千葉)
関東圏は全国でも特に高校生ボランティアが充実している地域です。
「どこに住んでいるか」で活動の特徴が少しずつ変わるため、地域ごとの色を知っておくと活動選びがぐっと楽になります。
東京は 種類の豊富さ、神奈川は 環境活動の強さ、埼玉は 地元密着型の安心感、千葉は 自然×体験型 が大きな特徴です。
保護者としては、
「移動距離は無理がないか」「安全な地域か」「帰宅時間は大丈夫か」
を考えながら選ぶと、安心して参加できます。
5-1. 都市部の特徴
都市部(東京・神奈川)は、公共交通の利便性もあり、1日完結型 のボランティアが探しやすいエリアです。学校帰りや休日に気軽に参加できる点が魅力です。
5-1-1. 東京:種類が圧倒的に多い
東京は関東圏の中でも“高校生可”のボランティアの種類が圧倒的に多い地域です。
市区町村ごとのボランティアセンターが充実しており、自治体・NPO・民間団体の活動が毎日のように更新されています。
【特徴】
・都市型イベントが多い(マラソン大会、文化祭、国際イベント)
・短時間・単発の募集が豊富
・語学を活かせる国際交流イベントも多い
・屋内の活動(図書館・美術館・博物館)も充実
・交通アクセスが良く、親の送迎が不要
【高校生に向いている活動例】
・イベント受付・誘導補助
・ミュージアムでの展示補助
・駅周辺の清掃活動
・子ども向けワークショップのスタッフ
・フードバンクの仕分け
【証明書の取りやすさ】
行政・大規模NPOが多いため、活動証明書が標準で用意されているケースが多いのがメリットです。
【基準】
東京で探す場合は「学校からの距離」「最寄駅からのルート」「夜の帰宅時間」を事前に確認します。
5-1-2. 神奈川:海岸清掃・子ども向け支援が強い
神奈川県は、海・公園・観光地という地域性を生かした環境保全系 の活動が非常に盛んです。
高校生にとっては「体験の手応えがある」「達成感が大きい」活動が多く、初めてのボランティアに向いています。
【特徴】
・海岸清掃(湘南、江ノ島、三浦など)が活発
・公園・緑地の保全活動が多い
・子ども食堂・地域支援が充実
・地元密着型NPOが多数
・防災イベントが盛ん
【高校生に向いている活動例】
・海岸のごみ拾い
・動植物の観察補助
・地域防災訓練のサポート
・子ども食堂の調理補助
・公園の清掃、植物の手入れ
【安全性】
海沿いの活動はスタッフの人数や危険区域の管理がポイントになります。
主催者が「高校生歓迎」かを必ず確認しましょう。
【基準】
「屋外活動が多い」という点を踏まえ、体調・天候・服装を事前に確認します。
5-2. 郊外の特徴
郊外(埼玉・千葉)は都市部ほどの数はないものの、地元で続けやすい のが最大のメリットです。
親の送迎や通学路に合わせて参加しやすく、初めてのボランティアとしても安心です。
5-2-1. 埼玉:地域密着の活動が多い
埼玉県は、自治体主導の地域密着型ボランティアが多く、
「家から近い」「短時間で参加できる」ため、無理なく続けられます。
【特徴】
・図書館・公民館の活動が多い
・子ども食堂の数が増えている
・スポーツイベントの補助が人気
・地元祭りや地域交流会での手伝いも豊富
・公共施設での活動が中心で安心
【高校生に向いている活動例】
・本の整理・読み聞かせ補助
・フードドライブの仕分け
・放課後子ども教室の運営補助
・地域のお祭りでの運営サポート
・スポーツ大会の準備
【証明書の扱い】
自治体主催の活動は証明書を発行してくれることが多く、推薦入試を考えるご家庭にも適しています。
【基準】
埼玉では「自宅からの距離」を重視して、負担の少ない活動を優先します。
5-2-2. 千葉:自然環境を生かしたボランティア
千葉県は、海と森に囲まれた地域性を活かし 自然体験型 の活動が豊富です。
体を動かすことが好きな高校生、自然が好きな子にとっては特に魅力的です。
【特徴】
・海岸清掃(九十九里・銚子など)が盛ん
・動物保護団体の活動が多い
・自然学習センターでの補助
・農業体験型ボランティア
・観光地でのイベント運営も人気
【高校生に向いている活動例】
・海岸の清掃・漂着物の仕分け
・保護犬・保護猫団体のサポート(高校生可か要確認)
・自然観察会の補助スタッフ
・農業支援の軽作業
・地域イベントの受付・誘導
【注意点】
自然系ボランティアは“移動距離が長くなる”場合があります。
活動場所が駅から遠い場合や送迎が必要なケースもあるため、事前チェックが必須です。
【基準】
無理のない移動距離・活動環境(屋内 or 屋外)を確認し、本人の負担が少ない活動を選びます。
〈行動〉地域ごとの募集を確認する
地域の特徴を踏まえたうえで、まずは次のように検索します。
「地域名+ボランティアセンター」
「地域名+高校生 ボランティア」
「地域名+単発 ボランティア」
各ボランティアセンターの募集ページは週ごとに更新されるため、
“気になる団体はブックマークして定期的に見る”のがコツです。
6. 活動証明書は必要?どう使う?
高校生のボランティア活動では、主催団体によって 「活動証明書(ボランティア証明書)」 を発行してくれる場合があります。
これは学校提出・推薦入試・総合型選抜・履歴書などで使うことがあり、保護者の方が最も気になりやすいポイントです。
ただし、証明書は 「あれば便利だが、証明書そのものが評価の中心ではない」 ことを理解しておくと、進路に振り回されず安心して活動を選べます。

6-1. 証明書の役割
ボランティア証明書には誤解が多い部分です。
親としては「証明書があれば評価につながるのでは?」と考えがちですが、実は評価の本質は別のところにあります。
6-1-1. 証明書は“事実の証明”であり、評価そのものではない
活動証明書は、
“〇月〇日に、〇時間、〇〇という活動を行ったことを団体が確認しました”
という 事実の記録 にすぎません。
書面があるから合格に近づくわけではなく、証明書だけで評価されることもありません。
高校生の進路指導では、証明書よりも次の点が重視されます。
・活動を選んだ理由
・そこで何を感じ、何を学んだか
・その経験を今後どう生かすか
・継続性があるか
・本人の言葉で説明できるか
つまり、「証明書=評価」ではないのです。
証明書は、あくまで “活動の裏付けを取るための安全網” として考えるとよいでしょう。
6-1-2. 大切なのは“継続した意欲”
大学入試の面接や推薦では、証明書以上に「意欲」や「姿勢」が問われます。
面接官が知りたいのは、
・なぜその活動に興味を持ったのか
・どんな場面で成長を感じたか
・どんな困難があり、どう乗り越えたか
・活動を通じて得た価値観は何か
といった 本人の内面の変化 です。
1日だけの活動でも深い学びがあれば価値がありますし、月1回の活動でも継続していれば立派な強みになります。
【基準】
証明書そのものより「活動の動機とふり返りの質」が評価されることを理解する。
6-2. 証明書をもらうときの基準
証明書の扱いは団体によって大きく異なるため、参加前に確認することが大切です。
6-2-1. 団体が公式に発行しているか
証明書を確実に発行してもらえるのは、次のような団体です。
・市区町村のボランティアセンター
・社会福祉協議会(社協)
・認定NPO法人
・自治体と連携しているNPO
・学校と協力している公的団体
こうした団体は 正式な書式 を持っており、学校や大学でも信頼度が高い傾向があります。
注意したいのは、
「個人が主催する小規模活動」「活動実績の少ない団体」「大学生サークルのみで運営」などの場合。
証明書を発行しない・形式が整っていないケースが多いため、事前確認が必須です。
【基準】
証明書が必要な場合は「公的な団体・認定NPO」を優先する。
6-2-2. 必要事項をチェックする
証明書として提出する場合、最低限そろっているべき情報があります。
【証明書に必須の項目】
・活動内容(何をしたか)
・活動日(いつ)
・活動時間(何時間)
・活動場所
・主催者名 / 団体名
・代表者の署名または押印
・連絡先(確認可能な電話や住所)
これらがそろっていない証明書は、学校側で認められないことがあります。
【保管のコツ】
・写真で保存
・スキャンしてPDF保管
・ふり返りノートと一緒に綴じる
後から必要になることが多いため、必ずコピーを残しておきましょう。
〈行動〉証明書が必要な場合は最初に聞く
活動後に「証明書はありません」と言われることを避けるため、
申し込み前に必ず 「活動証明書の発行は可能ですか?」 と確認します。
そのうえで、
・英語版の発行可否
・デジタル形式 or 紙形式
・記載内容
・後日の再発行が可能か
・学校側の提出形式に合っているか
も合わせてチェックすると安心です。
7. 親が今日からできる“安全と継続”のサポート
高校生のボランティアは、本人の成長につながるだけでなく、社会との接点を増やす大切な機会になります。
しかし、初めての活動は不安や緊張が大きく、本人だけに任せると負担が増えてしまうこともあります。
そこで、 親がそっと支えることで、活動が“安全に、無理なく、長く”続くようになる ポイントを整理します。
難しいサポートは必要ありません。
ちょっとした声かけや、情報共有だけでも、本人の安心感は大きく変わります。
7-1. 家族で共有すべき3つのポイント
高校生が安心して参加するためには、家族が同じ情報を持っていること が非常に大切です。
緊急時に「場所がわからない」「連絡が取れない」を防ぐことで、親子ともに安心して参加できます。
7-1-1. 活動先・時間・連絡方法を固定
まずは、次の3点を“同じ紙”または“同じメモ”で共有します。
・活動先の名前・住所
・集合場所と時間
・活動終了予定時刻
・連絡が取れる番号(本人 / 主催者)
・最寄り駅や交通ルート
特に単発ボランティアや、初めて訪れる場所は不安が大きいものです。
事前に地図を確認しておくと、「道に迷って遅刻しそう」という焦りを減らせます。
ポイント
・親は「困ったらすぐ連絡してね」と一言添える
・本人が地図アプリを使えるか確認しておく
・帰りの時間も大まかに共有しておく
こうした基本的な“見守り”が、安全につながります。
7-1-2. 本人のペースを尊重する
ボランティアは「毎週行くべき」「長時間活動すべき」というものではありません。
むしろ、週1回や月1回でも十分に価値があり、本人の負担が少ないほど長続きします。
・疲れている日は無理をさせない
・勉強や部活とのバランスを大切にする
・「続けられたらいいね」のスタンスで見守る
・行けない週があっても責めない
高校生は想像以上に体力や心の波が大きい時期です。
「続けること」が目的になりすぎず、本人のペースが尊重されると、自然と活動が習慣化していきます。
【基準】
“完璧を求めない”ことが、継続の第一歩です。
7-2. 小さく始めて続ける
継続の秘訣は「最初のハードルを下げること」です。
いきなり長期参加や大規模イベントに挑むと、疲れや不安が大きく、続ける前に心が折れてしまうことがあります。
7-2-1. まずは1日・単発から
最初は、負担の少ない1日だけの活動や、2〜3時間の短時間ボランティアがおすすめです。
・清掃活動(街・公園・海岸)
・イベント受付の半日サポート
・子ども食堂の仕分け
・図書館での軽作業
・フードドライブの整理
これらの活動はシンプルで理解しやすく、緊張が少ないため、初めての高校生に向いています。
本人が「楽しい」「できそう」と感じたら、それだけで大きな一歩です。
ポイント
単発で合わなかった場合は、他の種類に切り替えやすいのもメリットです。
7-2-2. 活動後のふり返りを記録
ボランティア活動は経験して終わりではなく、
“活動後のふり返り” があって初めて深い学びになります。
ただし、長文を書く必要はありません。
短いメモで十分です。
【例:3行ふり返り】
- 今日やったことは?
- どんな気づきがあった?
- 次にやってみたいことは?
これだけで、本人の中に“経験が蓄積”され、進路にもつながりやすくなります。
さらに、
・学校の提出物
・総合型選抜の志望理由書
・面接での質問
・活動証明書と合わせたポートフォリオ
などでそのまま活用できるため、将来の準備にも役立つ一石二鳥の習慣です。
〈基準〉
継続の鍵は 「負担が少ない」「安全」「本人に合っている」 の3つです。
この3つがそろうと、ボランティアは“義務”ではなく、“自分のペースで続けられる活動”に変わります。